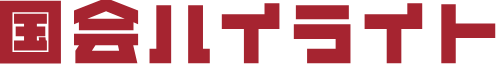赤旗2025年5月14日付

(写真)質問する小池晃書記局長=13日、参院財金委 |
日本共産党の小池晃書記局長は13日の参院財政金融委員会で、消費税減税とインボイス制度の撤廃を政府に迫りました。
小池氏は、石破茂首相が衆院予算委(12日)で、消費税減税を「まったく検討しないということはない」「これから議論はいくらでもやっていく」と答弁したことを挙げ、「消費税減税の影響を試算するのは当然だ」と指摘。加藤勝信財務相は「(首相答弁は)これまでの政府答弁とスタンスは異ならない」と試算を拒否しました。
小池氏は「御党とこれから先、議論する余地、可能性が多分にある」との石破首相の答弁(同日)について、消費税減税とあわせ大企業や富裕層に対する優遇を見直す「税制の抜本改革の議論をやろうじゃないか」と求めました。加藤財務相は「(与党税制改正大綱を踏まえて)法人税について検討する」と述べるにとどめましたが、小池氏は「自民党の中からも消費税減税の声があがっている。背を向けてはいけない」と批判しました。
小池氏は、インボイス登録した課税事業者が、前年の4倍の消費税納税を迫られ、途方に暮れたとの声を突きつけ、インボイス登録の取り消しを届け出ても、登録から2年たたないと免税事業者に戻れない“2年しばり”をやめるべきだと要求。消費税を一律5%にしてインボイスを撤廃するよう迫りました。
小池氏は「ストップインボイスの会」が行ったアンケート調査(速報版)で、登録事業者の77%が消費税や事務コストの負担を価格に転嫁できず、4割超が消費税などの支払いを所得や貯蓄から捻出し、1割超が借金で消費税を支払ったとの結果を示し、「財務省や国税庁が責任を持って実態調査をやるべきだ」と迫りました。