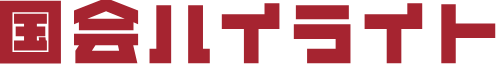赤旗2025年5月8日付

(写真)質問する小池晃書記局長=8日、参院財金委 |
日本政策投資銀行(政投銀)の特定投資業務を延長する法案が8日の参院財政金融委員会で自民、公明両党などの賛成で可決しました。日本共産党の小池晃書記局長は公的資金による大企業支援が拡大するとして反対。立憲民主党も反対しました。
特定投資業務は、政投銀が財政投融資特別会計(財投)からの出資金を元手に支援先に出資するもの。原資は政府保有株の配当などで、本来の支援対象は公益性が高く民間では対応が困難な分野に限られます。
質疑で小池氏は、特定投資業務の出資総額に占める資本金10億円以上の大企業の割合が97・8%に上るとして、大企業支援は「公的資金の活用にふさわしい審査がなければモラルハザード(倫理の欠如)になる」と指摘。西日本鉄道(福岡市)が沿線再開発のために立ち上げた不動産ファンドなどが出資先となっており、「不動産市場には国内外の投資マネーが流入し価格高騰を招いている。マンションの価格高騰は深刻だ」「公的資金を原資に不動産投資を過熱させることになれば大問題ではないか」と強調しました。
加藤勝信財務相は、特定投資業務が「投機マネーの流入のような不動産投資の過熱を招いてはならない」として、十分な配慮が必要だと答弁しました。
さらに小池氏は、財投の活用は下水道などのインフラの老朽化が深刻な自治体や医療福祉関係を優先すべきで、政投銀は資金の自己調達を強めるべきだと主張しました。